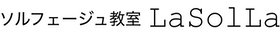和音の聴音
本日は、楽典にも、聴音にも関連する「和音の聴音」の話です。
さて、上記のような問題は、どうやって聴いていくのか?
横に聴くか、縦に聴くか?はたまたハイブリッド型(横+縦)か?
和音は上から読む?下から読む?
知っている人は知っているけれど知らない人は知らない話、実は和音は下から読みます。
しかも一挙に「ドミソー!」と読み上げます。
上から読んでいた人はまず和音を下から、しかもスラスラ読めるようにしてください。
聴く時も読む時同様に下から聴いていきます。
和音は下から、これポイントです!
一番下で鳴っている音を聴く
合奏や合唱をやっている人は、実体験で知っていること思いますが、音楽では上のメロディと同じくらい、一番下の支えが重要です。
和声でも同じで、一番下の音がなければハーモニーは支えを失い崩れてしまいます。
さらに面白い話を書くと、一番下の音が掴めると、段々と上に乗っている音群が想像できるようになります。
まず「一番下の音」を聴く、これもポイントです。
お悩み別攻略法
全く音が浮かばない
聴音の最中に小さくハミング一番下の音を歌ってみてください。
試験本番では出来ませんが、勉強中はやってもよいです。
また、机の上で鍵盤を抑える真似をして音を想像してみるなど、音をなんとかして取り出す努力をします。
考えすぎてわからない
どの音も鳴っているように聴こえたり、考えすぎてわからなくなる時があります。
そんな時は鳴っている和音の響きを、考えるのではなく感じとってみましょう。
明るい感じ?暗い感じ?もやもや?
響きから導き出せる答えもあります。
全く聴こえない時にもやれることがある
ここまで来てまったく「手も足も出ない!」という人もいるでしょう。
そういう場合は分析の勉強をしましょう。
攻略するにはまず相手を知ることです。
和音の仕組みを知っていると、聴こえ方は変化します。
◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。