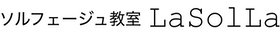Q&A
これまでに頂いた質問をまとめてみました。
ご質問がありましたら、こちらよりお寄せください。→お問い合わせ
-
小・中学生対象のオンラインレッスンはありますか?
-
オンラインレッスンは高校生以上でお受けしています。
小・中学生の生徒さんはまだ細かなフォローが必要なので、対面レッスンのみでお教えしています。
-
部活との両立は可能ですか?(高校生より)
-
前向きで、体力があって、努力家であれば、出来ないということはありません。これまでの生徒さんを見てきていると、両立できるのは優先順位を音大受験にしている人なので、「自分は他の人とは違う!」というプライドを持てると、自然と良い結果が得られると思います。
-
高校受験でレッスンをお休み出来ますか?(お母さまより)
-
出来ます。但し慎重な判断が必要です。
空白期間はない方がよいですが、どうしてもという方には、12月までレッスンに来て1・2月の試験期間のみお休みするスケジュールをお薦めしています。「ソルフェの宿題が出来ないのではないか?」と心配される方もいらっしゃいますが、状況を見ながらゆるく進めるので、息抜きになるとおっしゃる方も多いです。
-
聴音が出来るようになるにはどうしたらよいですか?
-
お会いしていないので、何とも判断が難しいのですが、やはりやさしいものを完璧に書きとることから始めるとよいと思います。
「音」はともかく真似です。普段から真似して歌う、弾く、ともかく耳を使ってください。ぼんやりしていた音が徐々に定まってくるのがわかりますよ。
「リズム」は型です。パタンを分析、叩いて感覚として体に入れる、そうすると少しずつ書けるようになります。叩くが先で、書けるのはその後です。
聴音をした後に必ず弾いてみてください。弾くことで自分の書いたものを客観的に検証できます。聴音はある種の特殊技術です。全く手も足も出ないという場合はプロに手解きしてもらいましょう。悩んで過ぎていく時間がもったいないからです!
-
コールユーブンゲンは独学で出来るでしょうか?
-
出来ます。
まずは学習計画作りから。曲数を数えて、入試までの期間で割って1週間何曲ずつと決めてとりかかります。
練習はともかく正確さを一番において、特にリズムがしっかりおさまるように意識します。
本番ではピアノを触れないことも多いので、練習でもピアノ使用は最小限にしましょう。
仕上げはスマホを使います。録音して気になる箇所を楽譜にチェックして、その曲を仕上げます。コールユーブンゲンは暗譜するぐらい歌い込んで、ようやく落ち着いて歌えるレベルになります。暗譜を目指して歌いましょう!