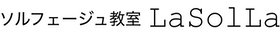聴音のいろは〜単旋律聴音〜
突然ですが聴音、どのように書いていますか?
書けるのであればどのように書いてもよいのですが、一般的な効率の良い書き方というのがあります。
今日は本当にはじめての人に向けた書き方を紹介します。
まずは目印になる音を拾う
聴音で、聴いた音をそのまま書くのは難しく、大抵の人が途中で手が追いつかなくなります。
では「全て暗記してから書こう」という作戦、その考え方は間違っていないのですが、みんなが出来ることではないです。
そこでよくやる方法が、まず目印になる音だけを拾うこと。
ここでの目印とは各小節の先頭の1音です。
8小節であればたった8個ですから、不可能な数ではありません。
まず目印を決めてから書き進む利点は、もし手が追いつかなくなっても次の目印からまた書き始めることが出来ること、また拍を意識して聴くことができるので、自分が今どこを書いているのか迷子にならないこと、です。
横に流れる音楽で、縦の刻みを感じながら聴くというのは難しいのですが、意識すれば必ず出来るようになります。
(私もそうですが)途中で手が追いつかず書けなくなる人は、その他大勢がやっている頭の音をマーキングすることからやってみてください。
聴音の流れ
1)音部記号と拍子、必要な数に小節を区切る。
2)1回目の通しで、全ての小節の「頭の音(1拍目)」を書く。
*最後の小節は耳に音が残っているので、先に仕上げてしまいます。
3)2回目・3回目と音が鳴る間に、残りの音を書き足していく。
4)同様に棒を引く。
*慣れると3)と4)は同時進行できますが、最初は音を書いてしまってから棒を引きます。
5)時間が余ったら、見直しをしながら音符を整える。
ある程度の数をこなすことで階段を登れると思ってください。
そしてその階段は、ドンと上がってしばらく停滞期があり、またドンと上がるイメージです。
二声や四声の聴音は、単旋律聴音がとれるようになってからです。
試しにやってみるとわかりますが、音が上やら下やらこんがらがって書けないです。
目印が書けない場合はトントン
拍感が曖昧な人だと、「目印の音が逃げてしまい書けない!」ということがあります。
そんな時には、拍をしっかり掴む練習が先です。
具体的には、課題の該当小節の真下で指でトントンしながら音を聞きます。
ポイントはただ指をトントンするだけではなく、楽譜の上でトントン、しかも今音が鳴っている小節に指をわざわざ持っていってトントンすることです。
こうすることで、耳だけでなく、視覚として今音がどこまで進んでいるのかが理解できます。
このトントンが最後までずれずに刻めるようになることは、基本スキルの1つです。
時間をかけずに書くコツ
「物凄く時間がかかる」という悩みを聞くことがあります。
この悩みを抱えている人は真面目な方に多い印象。
時間をかけずに書くコツは、ずばり「完璧に書こうとしないこと」です。
「どうしても定規を使って音符を書きたい!」そんな人もいますが、聴音の時は時間が限られているので、フリーハンドで書きます。
綺麗に書こうとする気持ちは大切にしてほしいのですが、時間に制限があるので、課題提出の時の譜面とは違うものになります。
棒は曲がる、たまはイビツ、確かに譜面は読みにくくなります。
しかし、書いていくうちに段々と書き癖が定まり、それなりに読める譜面になっていきますので、その変化をお楽しみに!
また聴音では、考え込まずとも「ミだ」「タイだ」と直感で閃く力が必須です。
まだ閃かないという人は、耳の経験が足りていないということなので、歌ったり、叩いたり、弾いたり、音楽と触れている時間を増やしましょう!
聴こえ方は千差万別
最後に、聞こえ方は千差万別で、誰もが出来るようになる秘訣はありません。
しかし自分の耳に替えはなく、この耳とお付き合いするしかないです。
諦めず、粘り強く、開拓していきましょう!

◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。