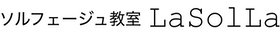属七の和音の勉強法(1)
四和音の中でも最初に覚えるのが「属七(ぞくしち)の和音」です。
スター的存在で出現頻度も高くよく知っている響きなのですが、どこに出てきたか問われると答えられなかったりします。
アンサンブルをしている時など、演奏している最中にこそ響きを味わいたいですよね。
どうしたら耳で判別できるようになるのか、自分で出来る「響きを掴む勉強法」を紹介します。
属七の響きを手に入れる練習法
歌ってみよう
「知識として属七の和音は知っているけれど、どこに出てきたかさっぱりわからない!」
そんな人にお薦めなのが「歌うこと」です。
属七の和音は特徴があるので、他の四和音よりも段違いに覚えやすいです。
但し、聴いているだけでは曖昧なままです。一度自分の体の外へ出してみましょう。
声に出して歌うとかなり掴みやすくなります。
以下はハ長調の属七ですが、これを1音ずつ「下から上へ、また下へ」と、山登りをするように歌います。
(ピアノ使用は根音のみ、なぞると答えがわかってしまうので声のみで歌います。)
次に、根音をGからFに変えて歌ってみます。(F・A・C・Es・C・A・F)
このようにどんな音からでも属七が歌えるように訓練します。
何調であろうと属七の響きは同じなので、様々な音から歌うことで、響きをインプットするわけですね。
(この書き方でやり方がわかるでしょうか?わからなかったらメールをください!)
弾いてみよう
次は弾く練習です。様々な場所から属七を弾いてみます。
ただ弾くのではなく響きを感じて弾くのがポイントです。
食べ物と同じです。ただ口へ放り込むのではなく、味わうと満足感が一段上になりますよね。
しっかり味わって自分の中に響きを染み込ませましょう!
さてここで少し分析の話です。
↓以下の譜例は、ハ長調の属七の和音がⅠ度に進行しています。
属七はこのように進みたい方向をしっかり持つ和音で、この特徴が判別の大きなヒントになります。
*限定進行音(赤い矢印、青い矢印)を明確に覚えるために、あえて右側の音を省略しています。
エクセサイズですが、これを様々な調に移調して弾きます。
一番下の音を見るとわかるように、Gから始まりF,E…と下りていくので、右手の親指が白鍵を1つずつ並行移動していくイメージで弾きます。
覚えないと響きに集中できないので丸暗記。慣れると20秒で弾けますよ。
7の和音では緊張を、そうでない2つの音では安心感を得られると思います。
「ぎゅーっ・ほっ」といった感じ。これを味わえれば満点です。
いつのまにか「あっ属七でてきた!」と判別できる耳になっていきます。
直感的にわかるところまで
目で見て属七と判ることも大事ですが、響きが体に入っていなければ演奏に役立てられません。
どの調であっても「属七」がわかり、「解決する方向」も直感的にわかるところまで目指しましょう!
まとめ
属七の和音は、歌ったり弾いたりして自分のものにしましょう。
「おっ属七だ!」と感じられる耳が持てると、演奏していて楽しいですよ。
◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。