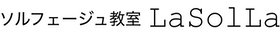暗記・記憶聴音のレッスン
先日中学生に行ったレッスン例です。
この日の題材はラモーの「メヌエット」ハ長調でした。
出来るだけ本物に触れてほしいので、名曲から選ぶことが多いです。
中学生にしてはやさしい課題ですが、難易度はその生徒にあわせて変えていきます。
暗記のレッスン方法
準備
調と拍子は最初に伝えます。
今回の生徒には7、8小節の左手部分は難しいので、あらかじめ答えを生徒のノートに書き込みました。
こんな感じでやる気を失わないように難易度を調節します。
聞く
まず一回聞いてもらって、どんな特徴があるか一緒に考えます。
「前半と後半の右手が似ているけれど、左手は違う」などと、形式の特徴に気づくことができるのが理想ですが、なかなかそうはいきません。
一回弾いただけでわからない時は、もう一回弾いたり、ヒントをだして気付けるように声をかけます。
暗記
「3回弾く→生徒が覚えて弾く」を1セットとして、暗記できるまで何セットか繰り返します。
書く
弾けるようになったら楽譜に書き起こします。
「書いている最中に迷ったら、いつでもピアノを弾きに戻ってきていいよ!」と声をかけます。
実際に忘れてしまっても、ピアノに戻って弾くと手が覚えていて、音を思い出せるものです。
弾く
書き上げたら普通は◯をもらっておしまいなのですが、私は生徒に書いた楽譜を見て弾いてもらいます。
実際に弾いてみると、正しく書けたか生徒自身でチェックすることができ、貴重な機会になります。
移調したり、今回の曲のように続きがあればそれを最後まで初見したり、どんどん拡げていけます。
「暗記→書く」が出来るサインとは
暗記・記憶聴音では、本来は弾く工程なしに「暗記→書く」という力を付けないといけません。
ところがそれほど簡単ではないので、上記のように「暗記→弾く→書く」という1クッションを挟みます。
めでたく「暗記→書く」に移ることができるサインは、「3回弾く→生徒が覚えて弾く」を1セットで出来るようになった時です。
当初5〜6セット繰り返しても覚えられなかった生徒が、少しずつ出来るようになるのは、私にとっても喜びです。
◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。