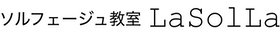「音程」を早く習得する方法
楽典問題の定番に音程を答える問題があります。
これが怒涛のように続く問題集というのがあって、訓練にはなるのですが面白いはずもなく、段々虚しくなってきます。
少なくとも私はそうでした。(笑)
そこで、教えるようになってからは、もう少し楽に勉強する方法はないかと考えました。
試してみたのは何かのついでに勉強する方法です。
聴音のついで、視唱のついでに「これ何度?」とたずねてみる。
ハンガリーの小学校でやっていたのを見たことがあり、そこからヒントを得ました。
この「ついでに勉強法」を小・中学生のうちからはじめておくと、いつのまにか音程がわかるようになっていきます。
とても良いのですが、欠点は時間がかかること。
受験まで時間がない場合は、やはり問題集をやるしかないです。
「音程」は楽典の教科書でも最初の方に出てきて、出来ないと「和音」も「移調」もちんぷんかんぷんです。
演奏にも100%役立てられるので、頑張ってマスターしましょう!
◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。