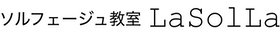アンサンブルの難しさ
一年に一度のリコーダーの音楽会が終わりました!
以前、留学時代の先輩・K先生のブログを読んでいて思わず頷いてしまったのですが、アンサンブルでは演奏技術はもとよりコミュニケーション能力が重要な要素になっています。
特にリコーダーアンサンブルは、全員が持ち替え可能なので、担当する楽器を替える度に自分の役割が変わります。もしかしたら担当する楽器によって性格まで変えなくてはならないかも?
当然意見がぶつかることもありますが、ぶつかったままでは音楽は作れないので、少しずつ譲り合いながら作業は進みます。互いを理解しあえるようになるととても良い音楽が生まれますが、いつしかぶつかり合いに疲れ、新鮮さが薄れ、グループの分解がはじまります。これは何もアンサンブルに限ったことではなく、何かグループを組んだ時の宿命のような気もします。
人によっては、「そんなことは面倒だからソロでいいじゃない!」と思うかもしれませんが、アンサンブルにはソロにはない素晴らしい魅力があります。喜びも苦しみも倍増し、時間が濃くなると言ったらよいか。だからこそ誰もがアンサンブルを組みたがるのだと思います。私の先生は「同じメンバーで何年も続くのは奇跡に近い。」とさえ言います。
アンサンブルを組むと、改めて音楽を続けるために何が必要かを考えさせられます。関係がないようにも思えますが、人間力を養うこと、音楽家にとって思った以上に大事なことなのだと感じます。

◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。