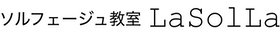調号が多くて読譜で構えてしまう
今日は、沢山調号のついた楽譜についてです。
調号の多い譜面が苦手な人はとても多いです。大人になれば読めるかといえばそうでもなく、子ども時代の苦手をそのまま一生持って回る方も多い。弾く曲も限定されるので深刻な問題です。
日本のピアノ教育では、『まずハ長調で基礎力をつけ、その後少しずつ調号を増やす』という指導法が主流でした。今でこそ考えが変わり、就学前からGdurやFdurを弾いたり、移調をさせるようなテキストも出ていますが、以前としてハ長調の分量が多いことに変わりなく、調号のついた曲を弾く経験が不足気味です。
私自身も教え始めの頃には、聴音や視唱の課題は♯♭3つまでしかやっていませんでした。理由は入試に出るのが3つまでだから。そんなことをしていると生徒が経験を積めないのに、当時は重要なことだと感じていませんでした。なんと浅はかな考え!
調号についての考え方を変えてくれたのが、ハンガリーで受けたソルフェージュ授業でした。
イルディコ先生は調号が幾つであっても平気な顔で楽譜を出してきました。「こういう作品が存在するのだから読むしかない」と、特にフォローもなしです。最初は戸惑いましたが、すぐに慣れました。慣れた理由は「移動ド唱」です。
ハンガリーでは固定ド唱もさせますが、移動ド唱をメインで教えます。そのメリットの1つに「調号が何個付いていようと楽に読める」というのがあります。実際授業では、視唱が苦手だった韓国人のクラスメートが、どんどん読めるようになりました。移動ド唱の効果を目の前で見せつけられた出来事でした。
さて、これをどう自分のレッスンに取り入れるかなのですが、私が取り組んでいるのは3つ「調号の多い課題も気にせず取り入れる」「移調を沢山やる」「移動ド唱もやる」です。
調号アレルギーがなくなると世界が拡がります。自信がつくので、結果として音楽がもっと面白くなります。

◎ソルフェージュ教室・ラソラ◎
千葉県柏市で音大受験準備レッスンをしています。